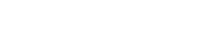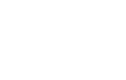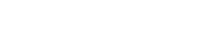カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2026年2月 (2)
- 2026年1月 (9)
- 2025年1月 (3)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (13)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (6)
- 2022年2月 (3)
- 2022年1月 (4)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (7)
- 2020年12月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年2月 (1)
- 2020年1月 (6)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2019年5月 (6)
- 2019年4月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2018年11月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年2月 (3)
- 2018年1月 (5)
- 2017年10月 (2)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (3)
- 2017年7月 (3)
- 2017年6月 (1)
- 2017年4月 (1)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
最近のエントリー
ブログ 7ページ目
開智中学合格!!
おめでとうございます!
(おおぞら学習塾)
2020年1月13日 14:47





社会の知識畑更新【中学入試によく出る社会の法律名など】
今回は【中学入試によく出る社会の法律名など】です。
年が明けて、今年の中学入試もスタートしています。
入試本番の確認に是非役立てて下さい。
(おおぞら学習塾)
2020年1月13日 14:38





理科の知識畑更新【中学受験によく出る理科の例外】
今回は【中学受験によく出る理科の例外】です。
分類や法則を覚えるには、物事の性質や特徴を理解するのは当然ですが、
そこに『例外』はつきものです。
例外だから覚えなくてもいいや、と高をくくっていると、
そういって切る捨てたものに限って出題されてしまうのです。
逆に、「これは出題されないかも、でも一応やっておこう」と思って成功したこともあります。
今回はその、「やっておけばよかった!」だけでなく、「やっておいてよかった!」の経験にも基づいて、
理科のいろいろな『例外』を、●●だけど▲▲という形式で紹介してあります。
目指せ、例外マニア!?
(おおぞら学習塾)
2019年11月 3日 15:56





社会の知識畑更新【中学入試によく出る社会のアルファベット略称】
今回は【中学入試によく出る社会のアルファベット略称】です。
大半が英語表記での頭文字で表しているので、
英語を本格的に習っていない中学受験生は丸暗記に近いものになってしまいますが、
日本語表記での正式名称とともに覚えるようにしましょう。
もちろん、機関の名称であれば何を行っている機関なのか言えるようにするすることも大切です。
(おおぞら学習塾)
2019年9月 4日 19:06





理科の知識箱更新【中学入試によく出る試薬+α】
今回は【中学入試によく出る試薬+α】です。
試薬とは、物質を化学的な方法で検出するのに使う薬品のことです。
ですので、液性(酸・中・アルカリ性)を調べる薬品は「指示薬」といい、試薬ではありません。
また食紅は道管の判別で使うので、試薬とはいえないかもしれません。
つまり「+α」とは、試薬ではないけど実験などで登場する薬品も加えました、という意味です。
近年は実験から考察する問題が増えています。
正確に判断できるようにしましょう。
(おおぞら学習塾)
2019年8月 1日 17:48





夏バッヂ出来ました
前回に引き続き、今回は赤色です!
夏の燃えるような太陽をイメージして赤にしました。

夏期講習会、頑張りましょう!!
(おおぞら学習塾)
2019年7月 9日 21:18





理科の知識箱を更新【中学入試によく出る理科の食品】
今回は【中学入試によく出る理科の食品】です。
よく出題される中学受験の入試問題で、
ジャガイモのイモはどの部分で、サツマイモのイモはどの部分ですか。
というものがあります。
定番なのでみなさんよくご存知かと思いますが、答えは
ジャガイモ→茎(地下茎)
サツマイモ→根
です。
中学入試にはこれ以外の野菜もたくさん出てきます。
アスパラガスはどこを食べているのでしょうか。
ブロッコリーはどこを食べているのでしょうか。
正解は『理科の知識箱』にてご確認ください。
野菜以外にも魚や加工食品についてもまとめました。
是非参考にしてください。
(おおぞら学習塾)
2019年6月 5日 21:46





カッティングシートが見やすくなりました。

以前のものと比べると、文字の部分がすりガラス調になっています。
夜は室内の光が文字の部分だけ抜けるので、
見やすくなっています。
缶バッヂのデザインでも登場した雲のキャラクターもいます。
是非近くでご覧になってください。
(おおぞら学習塾)
2019年5月31日 20:01





ちりもつもれば
毎週、新出漢字を8個ずつ学習し、その字を用いた書きとりの小テストを行うのです。
毎週毎週テスト勉強するのは大変ですが、受験直前に小学校の漢字をすべて復習するのはもっと大変です。
ちりも積もれば山となる、のことわざと同じで、コツコツと積み重ねていくことが結局合格への近道なのです。
小6の夏休みまでに小学校で習う漢字はすべて学習し終わりますので、
小6の夏期講習からは中学受験の入試実戦問題の漢字となります。
(おおぞら学習塾)
2019年5月22日 19:29





理科もそろそろ佳境です。
どの教科にもいえますが、小6の1学期はこれまでの受験勉強の中でもさらに難易度の高い内容になっています。
それもそのはずです。
夏休みまでにすべての学習内容を終えて、夏からは中学受験への実戦に入っていくのですから。
理科にしても同じです。
来週からは、圧力・浮力・ばね・てこ・滑車・輪軸と、受験物理のオンパレードとなっています。
ここからは計算問題が続くのですが、今週は小休止、最後の暗記分野でした。
『エネルギーと環境問題』についてです。
火力・原子力発電のメリットデメリットや、それにかわる再生可能エネルギー、
地球温暖化や酸性雨などを勉強します。
計算こそそれほどないのですが、最近話題になっている分野ですので中学入試問題への出題率も高まっています。
生徒さん達には、暗記分野だからといって侮らないでしっかりと理解してもらいたいです。
(おおぞら学習塾)
2019年5月15日 20:24





<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>
100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。